希望の車いすとは

始まりは一人の母親の思いから。
メリー・ペナー宣教師の息子ダニエル君は3歳で進行性の難病と診断され、車いすの生活を余儀なくされました。幸い日本の医療と福祉制度のおかげで、体の成長に合わせて4年ごとに新しい車いすをもらい、学校にも家族で旅行にも行くことが出来ました。
2000年の秋、ペナー氏は使われなくなった車いすを回収・修理して、困っている人に贈る活動を始めました。2002年に最初の車いすを中国に贈り、とても喜ばれました。この働きに徐々に協力者が集まり、2006年に「希望の車いす」の組織が出来、2008年2月にNPO法人となりました。以来、人種・宗教そのほかどんな違いにもかかわらず、アジアの車いすを必要としていても入手することが出来ずにいた方々を探し、日本で心を込めて整え磨いた、きれいな車いすを無償で贈り届けています。
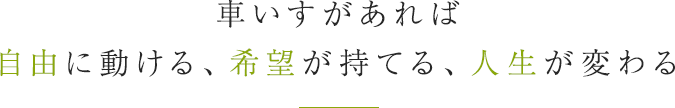
私たちは、車いすメーカー、リース会社、福祉団体、社会福祉協議会、個人などから、使われなくなった車いすを回収し、シニア、社会人、主婦、学生、障がい者など、様々なボランティアの手で洗浄、整備し、ピカピカに磨き上げ、蘇らせます。人の役に立てる喜びと、ボランティア同志の楽しい交流もあります。丁寧に整備して蘇らせた車いすは、海外各国のパートナーの手で、車いすを必要とする方々に届けられます。一台一台が、自由と希望を届け、受け取った方と家族の人生が変わります。活動費は、会費、寄付、社会貢献活動を支援する企業・団体からの支援で賄われています。
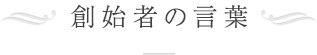
その日、空は青く、陽は輝き、そして私たちの生活が変わりました。私たちの息子に初めての車いすが届いたのです。それは明るい黄色の車いすでした。私は心からの感謝とともにその日のことは一生忘れないでしょう。
数年後、ジョニー エレクソン タダ さんが、車いすに乗って、世界巡回の旅で日本に来られ、アジアの子供たちのために車いすがどれほど必要とされているかについて語ってくれました。私はそれを聞いて、日本にいる私たちには4年ごとに、成長する息子の体に合う新しい車いすが与えられるのに、そんな恩恵の受けられない国々で生活する家族がいるのだ、と気づかされました。 キリストに従うものとして、私は自分にできることをしたいと思いました。
私は友人のえり子さんと一緒に、どうやったら、使われていない車いすを集めて必要な方のところに届けることができるだろうと考え始めました。今日、沢山の人々が一緒に車いすを集め、整備し、磨き作業に精を出している姿を見て感無量です。旅行者やビジネスマンたちはアジアの各国に車いすを届ける手伝いをしてくれています。私たち「希望の車いす」は、与えられた資金や人々の時間、力、才能などいろいろな資源を大切に用いて、質の高い仕事を続けようと努力し続けています。けれども、一番大切にしていることは、人々の生活が変えられていく、ということです。
最初のころ車いすを届けた人に、タイとミャンマーの国境付近に住むロト君がいす。若者は皆そうですが、ロト君も仕事で稼ぎたいと思っていました。地元のカヌー工場で細々と働いていましたが、車いすのおかげでより多くの仕事ができるようになり稼ぎが増えたそうです。数年後再会した時、ロト君は「愛車」を愛おしそうにさすりながら、「この車いすは僕の親友なんだ」と言っていました。
山形の田舎町で何年も前に始まったことが、今日の人々を変え続けています。車いすとともに「希望」が届けられています。
アジア諸国を中心に車いすを届けています
これまでアジア諸国への海外旅行者に各国の空港まで運んでいただき、現地パートナーに届けていただきました。2009年以降は、企業の協力を得て、毎年1~2回、コンテナで一度に125台程をまとめて輸送しています。

皆さまのおかげで2025年7月1日の時点で
3518台 をお届けしました
皆さまのおかげで 2025年7月1日の時点で3518台をお届けしました
| 国別 |
贈呈台数/台 |
| タイ |
1348 |
| フィリピン |
683 |
| カンボジア |
308 |
| ベトナム |
208 |
| モンゴル |
287 |
| ミャンマー |
289 |
| ウズベキスタン |
27 |
| マレーシア |
14 |
| 中国 |
13 |
| インドネシア |
3 |
| ナイジェリア |
1 |
| ジンバブエ |
1 |
| ガーナ |
20 |
| 韓国 |
1 |
| ブータン |
5 |
| ウクライナ |
302 |
| 東ティモール |
5 |
| バングラデシュ |
3 |
車いすの整備と海外発送を通じたSDGsの達成
私たちの活動は、使われなくなった車いすを整備し、海外に発送することを通じて、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に貢献しています。特に、目標8(働きがいも経済成長も)、目標10(人や国の不平等をなくそう)、目標11(住み続けられるまちづくりを)、目標17(パートナーシップで目標を達成しよう)に焦点を当てています。
目標8:働きがいも経済成長も
私たちの活動は、ボランティアの方々が自らのスキルや経験を活かして社会に貢献する場を提供しています。整備作業を通じて、彼らは新たな技術を学び、仲間との交流を深めることができます。このような活動は、彼らの自己成長を促し、地域社会における連帯感を高める要素となっています。
目標10:人や国の不平等をなくそう
車いすは、身体的な障害を持つ人々にとって、移動の自由をもたらす重要な道具です。しかし、発展途上国では、車いすの入手が困難な場合が多く、障害者が社会に参加することが難しい状況が続いています。私たちは、整備した車いすを必要としている国々に送ることで、障害者の移動手段を提供し、彼らの生活の質を向上させることを目指しています。これにより、障害者が教育や仕事にアクセスできるようになり、社会的な不平等を減少させることができます。
目標11:住み続けられるまちづくりを
私たちの活動は、持続可能な都市づくりにも寄与しています。車いすを必要とする人々が移動できる環境を整えることは、彼らが地域社会に参加し、生活の質を向上させるために不可欠です。整備された車いすが地域に広がることで、公共の場や交通機関がよりアクセシブルになり、すべての人が平等に利用できる社会を実現する手助けをしています。また、私たちの活動は、リサイクルや再利用の観点からも持続可能な社会の実現に寄与しています。
目標17:パートナーシップで目標を達成しよう
私たちの活動は、さまざまな団体や企業とのパートナーシップによって支えられています。地域の福祉団体や企業、国際的なNGOと連携し、車いすの整備や発送を行っています。これにより、資源の共有や情報の交換が促進され、より多くの人々に支援を届けることが可能になります。パートナーシップを通じて、私たちはより大きな影響を持つことができ、SDGsの達成に向けた取り組みを強化しています。
私たちの活動は、使われなくなった車いすを整備し、海外に発送することを通じて、SDGsの目標8、10、11、17を達成するための重要な一歩です。地域の雇用を創出し、障害者の移動の自由を確保し、持続可能な都市づくりを推進し、さまざまな団体とのパートナーシップを築くことで、私たちはより良い未来を目指しています。これからも、私たちの活動を通じて、持続可能な社会の実現に向けて努力していきます。皆様のご支援とご協力を心よりお願い申し上げます。